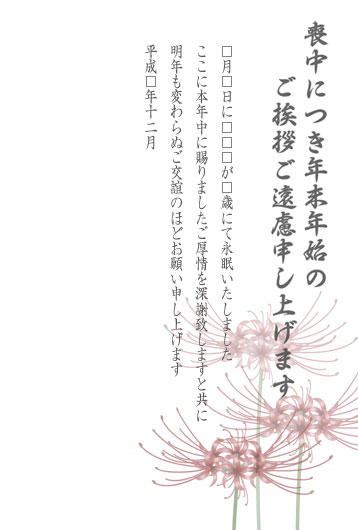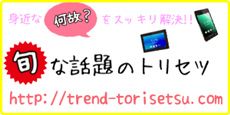By: MIKI Yoshihito
11月15日は七五三です。
子供の成長を祝う日本の古き良き伝統行事ですね。
七五三という行事は知っていても、
詳しい内容や由来などをあなたはご存知ですか?
お父さんやお母さんも知らないのではないでしょうか?
また、七五三の行事も同様です。
子供が生まれて2年が経ったころに、
「ちょっと七五三の写真やお参りはどうするの?」
なんて、おばあちゃんに言われてアタフタしているお母さんも多いのでは。
「七五三は三歳になってからお参りするの?」
「早生まれの子はいつ七五三をすればいいの?」
などなど、わかっているようでわからない事もあるはずです。
という事で今回は、
七五三の由来や、いつ祝うのがよいかなどの詳しい情報をお届け致します。
七五三の意味と由来
七五三は11月15日、子供の成長を祝って
神社やお寺などにお参りに行く年中行事です。
七五三の始まりは天和元年11月15日(1681年12月24日)に、
館林城主である徳川徳松の健康を祈って始まったとされる説が有力です。
もともとは関東圏の地方風俗だったものが、
京都や大阪など関西でも行われるようになり、
その後全国に広まったものです。
「七五三」という名称から、
その年齢に行う同じ行事のように思われていますが、
本来はそれぞれの年齢で行う別々の異なった行事でした。
七五三の発祥とされる関東地方では、
各々の行事は以下のように考えられています。
| 3歳 「髪置きの儀」江戸時代には、3歳までは髪を剃る習慣があったため、 それを終了して髪を伸ばし始める儀式です。 5歳 「袴着の儀」 男の子が袴を着始める儀式です。 7歳 「帯解きの儀」 女の子がそれまでの紐付きの着物に代えて、 |
旧暦の15日はかつては二十八宿の鬼宿日、
つまり鬼が出歩かない日に当たり、
何をするにも吉日であるとされました。
また、旧暦の11月は収穫を終えてその実りを神に感謝する月でした。
その月の満月の日である15日に、
神への収穫の感謝を兼ねて子供の成長を感謝し、
加護を祈るようになったのです。
明治以降は新暦の11月15日に行われるようになりました。
近年は各家庭でさまざまな都合があるため、11月15日にこだわらず、
10月中旬から11月前半の吉日や土日祝日などを利用して
お祝い・お参りを行うことも多くなっています。
11月15日を過ぎてからでも都合のつく日に、
というのも珍しくありません。
北海道などの寒冷地では11月15日前後の時期は
寒くなっていることから、1か月早めて10月15日に行なう場合もあります。
つまり、大切なのは子供の成長を祝うことで、
日にちなどにはそんなにこだわらなくても大丈夫ということです。
11月15日やその前の土日、祝日などは
特に七五三で神社が混み合いますので上手に予定を立てましょう。
七五三を祝う時期は満年齢?それとも数え年?

By: ChingHua Chung
伝統行事を行う時に迷ってしまうのは、年齢の数え方ですよね。
ややこしいことに、日本には年齢の数え方が「数え年」と「満年齢」の2種類があります。
数え年は生れた年を1歳とし、翌年を2歳と数えます。
正確には、お正月を迎えたら2歳なので、
12月31日に生まれた子は、次の日には2歳ということになります。
満年齢では、生れた年を0歳とし、
誕生日ごとに1歳ずつ加えていく数え方です。
私たちには、この満年齢の方が馴染みがあり、わかりやすいですね。
江戸時代に始まった神事なので
旧暦の数え年で行うのが正式となり、
昔は数え年でお祝いをしていました。
最近ではわかりやすい満年齢でお祝いするのが一般的です。
年の近い兄弟姉妹がいる場合、上の子の満年齢にあわせて、
下の子は数え年で一緒に七五三を祝うということもよくあります。
住んでいる地域や各々の家庭によっても
慣例がありますので、周りの人にも確認してみましょう。
また、7歳は歯が生え変わる時期でもあます。
最近は、
「せっかくの七五三の写真が歯抜けの笑顔になるのは残念」
という理由から、数え年で祝うという家庭も増えています。
自分の家庭の都合に合わせてお参りに行けるといいですね。
早生まれの子供は何歳で祝うの?
最後に、1~3月に生まれた早生まれの子はいつ祝えばいいのでしょうか?
早生まれの場合、何をするにも年齢で迷ってしまいがちですよね。
でも年齢の数え方は同じですし、
前述したように最近はあまりこだわらないことが多いので、
各ご家庭の都合や、お子さんの成長に合わせるのが良いでしょう。
3歳の七五三は、数え年だと2歳半とまだ小さいので翌年に回す人が多いようです。
3歳でも、着物を着せるだけで大変です。
長時間の参拝や写真撮影もありますから、
無理の内容に満年齢でお祝いする方がよいでしょう。
こちらの動画で、写真撮影の大変さがよくわかりますよ。
5歳、7歳の場合は幼稚園や保育園に通っている子が多いので、
園の行事やお友だちに合わせることが多いようです。
その年齢になると、地域や家庭の慣例に合わせて祝うこともできるようになりますよね。
まとめ
・七五三の由来と意味
・七五三は何歳で祝えばいいのか?
などの、七五三についてのアレコレをまとめてみました。
あまり細かいことにとらわれず、
いい思い出を残せるようにできるといいですね。
★おすすめ関連記事★
【七五三の服装】7歳の女の子に人気の袴と着物まとめ/洋服でもOK?